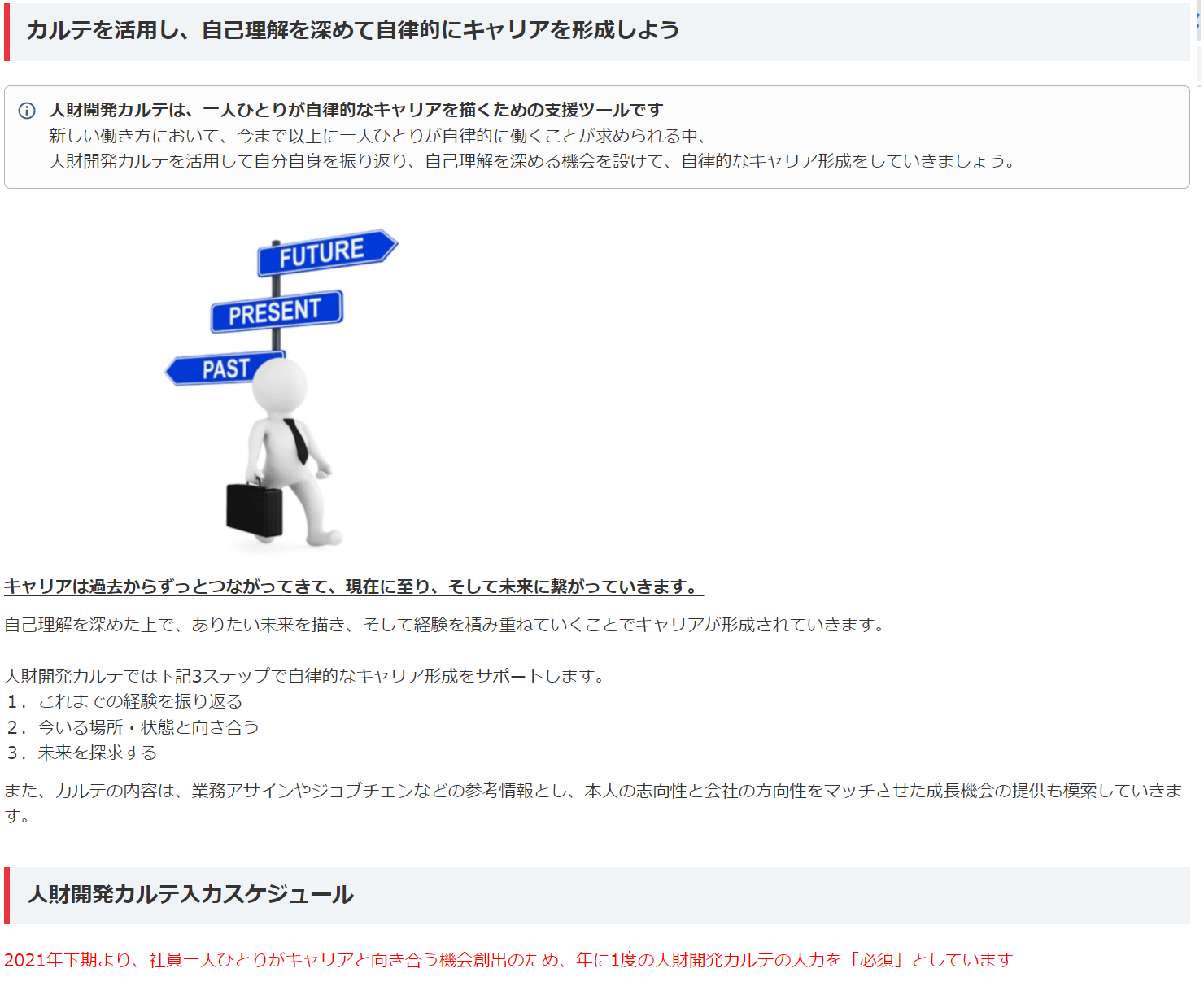ヤフーの文化として定着した「1on1」
当コンソーシアムでは、社員の自律的な働き方を支援する「キャリアオーナーシップ」の考え方を大事にしている8社の方々が集まって、この文化をさらに広げるためにどんなことが大事なのかを研究をしています。このコンソーシアムには御社が参加された背景を教えてください。
コーポレートグループ PD統括本部 ビジネスパートナーPD本部 本部長 岸本 雅樹(以下、岸本):弊社では1on1を2012年から導入していますが、「キャリア自律」を促すというのが目的の1つとして既にあり経営戦略上、キャリア自律の考えを大切にしてきました。
しかし、1on1を始めた2012年から比べると、日本にもジョブ型雇用の考え方が出てきたり、雇用の流動化がより進んだりしましたし、労働人口が減ってきたことでより個人が会社を選ぶ傾向が強くなりました。環境変化の結果、会社と個人との関係が変わってきている中で、2012年時点よりも「キャリア自律」が本当の意味で経営戦略において重要な一つのカギになってきているんです。
特にZホールディングス(※1)全体で考えると、ヤフーが属するZホールディングスは「日本・アジアから世界をリードするAIテックカンパニー」となることを目指しています。AIやビッグデータなどのテクノロジーが軸になる会社として成長し続けるには、もっと人材を増員していく必要があるんです。
グローバルな採用競争も起きる中、テックカンパニーにふさわしい「自律的に働ける人材」を今後もしっかりと獲得して活躍してもらうためには、選んでいただける会社になる必要があります。そうしないと、事業が立ち行かなくなってしまいます。会社にそれ相応の土台がないと、もう選ばれなくなるんじゃないかというのを非常に危惧しているんですね。
キャリア自律を促すプラットフォームとして会社を機能させていくにはまだまだ多くの課題がありますが、会社の外に目を向けてみても、人事施策に関してチャレンジが必要ないという会社はほとんど存在しませんし、色々な企業がキャリア自律を促すために、悩みながらも様々な取り組みをされています。そういった悩みを会社間で共有しながらキャリア自律を促していきたいというのが、コンソーシアムへの参加動機としてまずあります。
そして、そもそもヤフーのミッションは『UPDATE JAPAN』なんですね。自社だけに閉じるのではなく、日本の働き方や企業のあり方をよりよくしていきたいと考えています。働き方という観点から、日本をより良くアップデートしていきたいという想いがあり、どうすればそれが実現するためのヒントを知るために、コンソーシアムに参加させていただきました。

岸本さんのお話にも出ましたが、書籍で出ていたり、メディアに取り上げられていたりで、ヤフーさんの人事と言えば「1on1」というイメージがあります。実際にどれくらい定着していて、それが社員のキャリアにどのような影響を与えているのでしょうか。
岸本:1on1については、この10年推進していますが、今年2021年の6月に実態調査を行いました。
上長、部下、それぞれの観点でどのような効果を感じているのかというサーベイをとっているんです。
その結果からみると、約93%の社員が隔週で1on1を実施しています。2012年のやり始めた当初は「何の意味があるのか」「時間が取られてしまうじゃないか」という話もあったのですが、今そういうことを言われることもなくなりました。
今はもう昔のように「必ず毎週30分はやってください」などと人事部門からアナウンスするようなことはしていません。新たに管理職になった時には、1on1スキルの研修を行い、上司の立場になったときの必須スキルとして学んで頂いています。
2012年に導入した当初は、きちんと実施しているかを確認したり、どういう効果があるかの測定をするために「1on1チェック」というものを行っていました。開催頻度の点数や、部下から上司に対しての1on1に対する点数などをチェックし、点数の低い上司は研修を受けてもらって強化するなど、かなり強制力を強めに推進していました。
そのような積み重ねがあって、今ではヤフーの良いカルチャーとして定着しているんじゃないかと思っています。
一方で、質の部分ではまだ課題を感じています。弊社は、全社員を対象に360度のフィードバックするためのサーベイを行っていて、部下から管理職のフィードバック項目に「管理職の人はあなたのキャリアに気づきを与えてくれていますか」などの、1on1の質に関わる項目を入れています。
その結果を見ても、コンソーシアムのテーマである「キャリアオーナーシップ」の醸成にきちんとつながっているかどうか、個人のパフォーマンスを最大化できているか、社員の成長を促せているか、それらの点については、1on1のやり方を見直しながら、もっと強化していく必要を感じています。
※1 ご参照:Zホールディングスについて
https://www.z-holdings.co.jp/pr/press-release/2019/0425/
現在、ヤフーさんはリモートワーク中心の働き方に移行されています。ますますコミュニケーションの機会が限定されますし、そのような状況の中で1on1の意味というのはこれまでよりも重くなると思っています。コロナ禍になり大きな環境変化があったわけですが、この不確実な状況に向き合う上で、1on1が組織文化になっていたことによりどのようなメリットがあったと考えていますか。
岸本:1on1の文化があることで変化に適応できたという要素はあると感じています。常日頃からコミュニケーションをとることにより、上司と部下の信頼関係がつくれていたのは大きかったです。
急に会えなくなって目が届かなくなっても、普段の信頼関係があり、部下の方からも気軽に上長に話せるようになっています。信頼関係ができていないと、より話しづらくなったり、より仕事がやりづらくなったりすると思うのですが、普段の関係構築ができていたため、もちろん課題が0というわけではありませんが、リモートワークに移行してもそこまで大きな影響は出ていません。
コーポレートグループPD統括本部ビジネスパートナーPD本部 組織・人財開発部 部長 木下 学(以下、木下):1on1のおかげでリモートワークへの移行がスムーズにできたのは大きかったです。リモートワークになると、Zoomなどをつながない限りは相手と接続されない状態になりますが、ヤフーではリモートに切り替わってもコミュニケーションのベースが既にあるわけです。1on1がコミュニケーションのハブとしても機能しているんですね。これは副次的ではありますが、導入メリットの1つだったと感じています。
選ばれる会社づくりに必要な「社員との対話」
ヤフーさんは「アライアンス」「イコールパートナー」というキーワードをコンソーシアムの研究会の中でもおっしゃっているのが印象的です。会社と社員が対等な「イコールパートナー」になっていく上で、会社としては今後さらに何を充実させていきたいのでしょうか。

木下:1on1は自律を促すための軸となるツールですが、それに絡めて進めているものでいうと「人財開発カルテ」があります。自身のキャリアやスキルを記録するレジュメのようなものです。
キャリア自律をしようと思ったら、自分の現在の立ち位置をしっかり把握し、自己理解を深めることがスタートラインになります。カルテは、1on1を通じて、社員自身の立ち位置の認識合わせをするためのツールです。
今まで自分はこんなことをやってきた、これが今はできる、今後はどうしていくのか……などなど、自分で一生懸命に言語化したレジュメを見ながら、中長期的なキャリアについて上長と一緒に考える機会をつくっています。
ただ正直言うと、現状だと任意で運用しているので、まだ利用率が1on1ほどは高くないんですね。これを1on1のように8割、9割の社員が活用して、自己理解を深めることが習慣化すれば、社員のキャリア自律がさらに進みやすくなると考えています。
また「人財開発会議」というフォーマットもあります。これは直属の上長に加えて関連部署の役職者が集まって「人財開発カルテ」をもとに一人一人の中・長期的な育成方針を話し合うというものです。社員が自己理解を深めようと思った時に、上司だけではなく、それ以外の役職者からフィードバックを受けられる機会なんですが、外からのフィードバックはキャリア自律を促す上でとても大きな影響があります。これも、より多くの人が当たり前に活用する状態にしていけたらと考えています。
岸本:その他の制度でいうと、キャリア自律の一環として自分の人生をどう歩むのかを振り返る機会として、サバティカル休暇を6年前から制度化しています。しっかり内省して、自己認識を深め、自分のやりたいことを考えていくことがキャリア自律においては大事ですが、会社の中でずっと仕事していると、なかなか振り返りきれない部分があります。けれども、ちょっと1回立ち止まって、じっくり深く内省したいタイミングは誰しもあると思うんですね。
社内でも議論して、社員の「内省」と「学び直し」を促すために、最長3ヶ月の休暇がとれるように制度設計をしました。基本的に理由は問わず、申請すれば10年以上勤続した社員は誰でも取ることができます。
そもそも、サバティカル休暇は「1人のヤフーのメンバーである以前に、みんなそれぞれに自分の人生がある」という思想を元につくられています。前社長の宮坂の表現を借りると「自分は自分の人生の社長」ということですね。どう歩んでいくかは、自分自身でマネジメントしないといけないですし、しっかり意識するべきだよね、という考え方がベースにあります。
「キャリアオーナーシップ」を社内で醸成するにあたって、現状どのような課題を感じていますか。
岸本:キャリア自律しているプロフェッショナル人材が、会社・組織の中でしっかり自律的に働けているかに課題意識を持っています。
他の会社でも働けるような方が、主体的に会社に対して成果を出したり、やりがいが高い状態になっているかが重要です。そのためには、本人のやりたい方向性と会社が求めているものが、究極的には完全一致することが一番望ましい状態ですが、やはり様々な事業を会社として行っているので、100%の一致をつくるのが難しいのが実情ではあります。
本人とのマッチ具合を高めて、やりがいのある会社にするために、我々も努力しなければならないですし、社員ともさらに対話をしていかなければならないと考えています。
木下:「対話」という面で言うと、エンゲージメントをきちんと測っていくことが大事だと考えています。現状では、毎月、サーベイで測っています。
サーベイの結果をみても、まだまだ社員一人一人が、ヤフーで働いている意味を主体的に語れるような状態にはなっていないのが現状です。ここは成長ができるのか、いい経験ができるのかという判断軸で社員は会社を選ぶわけですが、そう思ってもらえる会社になるためには、まだまだ課題があるなという認識です。
しかし、例えばリモートで働けるという環境面だったり、業務の幅の広さだったり、役に立つ経験の広さを考えると、ヤフーは本当に良い資源がたくさんあるんです。実際にヤフーを選んでいただけた後に、これらの資源を上手に活かして、成長の機会にしていただけているのかについては、サーベイなどを通じて、しっかりと測っていきますし、その結果を元に適切なフィードバックをしていけるかどうかがポイントになってくるなと感じています。
加えて、1on1の質をいかに上げていくかが大事ですが、質の向上には、直属のマネジメントが何を観察して、日々何を発するかが大きく影響します。そのため、2021年度下期の11月から、1on1の質の向上を目的とした新しいトレーニングプログラムを、マネジメントに向けて提供を開始しています。具体的な目標の「達成支援」、部下の自己認識を促す「内省支援」、そして「キャリア自律支援」の3つの要素を1on1で満たしていこうと伝えています。
アセスメントを用いて1on1の今の状態を計測し、マネジメント側からどのような問いかけを部下にするとスコアの改善につながるのかというやりとりが、質の向上においては不可欠だと考えていて、その方法について議論を進めているところです。
多様な個を活かして、組織のパフォーマンスを最大化する
ホールディングス制を敷いて以降、いくつかの大きな資本提携が起きました。それぞれに個性やカルチャーが違う会社が一緒になるという大きな環境変化の中で、それぞれの文化をどのように風に馴染ませて、どのようにアップデートしているのか、今時点での取り組みなどを教えてください。

岸本:おっしゃる通り、ZOZOが加わったり、LINEと統合したりすることで、事業の幅も広がってきましたし、様々なカルチャーの企業が合わさることになりました。その中で思うのは、より変化に適応できる、自律・自走できる社員が経営戦略上必要になってくるということです。
グループ内において、環境の変化はますます目まぐるしくなります。その中で大事なのは、社員が自分で判断したり、その環境を自分のプラスにして楽しく仕事体験をつくっていけることです。それができる自律した社員の育成が、事業戦略を達成する上でもますます必要だと思っています。
現状だと、カルチャーや仕事の進め方でまだまだ課題がたくさんありますが、これまでの考え方に固執していては、解決できないと考えています。柔軟に考えて、自分なりの最適解を見つけて、周りの人を巻き込みながら合意に持っていくというプロセスが文化の違う人が交わるチームにおいては大事ですし、これは会社から明確に「こうやってください」とは言えない部分なわけです。
そしてダイバーシティ&インクルージョンという考え方からも、この多様な個を活かして、どのように組織のパフォーマンスを最大化していくかというのも大事だと思っています。
Zホールディングスは本当に多様な組織体になっているので、秘めている可能性を最大限発揮できる組織へと成長させることが、ものすごく大変ですが、挑戦しなければいけないテーマになっています。
それを実現するために大事なのは「対話」です。これまで大事にしてきた1on1を軸にして、これをより広げて、文化の違う他者とコミュニケーションをとって、お互いの理解を深めていく。そのような機会づくりが必要です。
そもそも、各社それぞれにこれまで積み上げてきたすごく良い価値観を持っているんです。それを消して1つにまとめあげるのは「インクルージョン」とは違いますよね。各社ごとに全然違う強みを持っているからこそ、良いところをお互いに伸ばして融合していくことで、より良い組織にできるという観点が大事なんです。
多様性を保ちながら、多様なサービスを多様な方々に提供していく組織でありたいですし、それを成し遂げる上で大事なのは「共通のゴール」で、これをもっと明確にしていきたいと考えています。
これからますます質の高いアウトプットが求められる中で、コンソーシアムからどのような成果を生み出したいですか。
木下:個々人の「キャリア自律度」を測定できるようなものさしがつくれるといいですよね。「今ここで仕事をしている意義をちゃんと自分の言葉で説明できる」とか「セルフモチベートができる」とか、キャリアオーナーシップ人材に共通する要件があると思っていて、それを確認して可視化できると面白そうだなと思います。
岸本:今は人事が「キャリア自律をしよう」と発信していますが、実際に普段から社員がキャリア自律を意識して普段過ごしているかと言うと、まだそういう状態にはなっていません。自分自身でキャリア自律の認識を深めるためにも「キャリア自律度」のような指標があって数値化されると、内省をより促せるかもしれないなと思います。それはあくまで1つの例ですが、個々人のキャリア自律への意識づけが自然と進むような取り組みを生み出したいですね。
ヤフーさんは短い期間で規模が大きくなり、大企業と呼ばれるようになってきたことで、入ってくる人材のチャレンジに対する考え方なども年々変わってきていると思います。社員にチャレンジを促していくような環境にしていくために、今、何が必要とされているとお考えでしょうか。
岸本:我々のキャリア自律の促し方を整理すると「1on1」という軸があり、サポートツールとして「人財開発カルテ」があります。ただ、1on1などで話したことを実践できる仕事の環境を与えられないと、この会社ではキャリアを描くことを諦めてしまうと思うんですね。キャリアを社内で提供する機会づくりまで、セットで設計していくことが今後必要になってくると考えています。
ジョブチェンという仕組みで社内異動を促したり、新規事業の公募をしたりと、いくつか制度はありますが、まだまだ機会は限られているので、チャレンジしたいと思っている気持ち、つまり「内発的動機」をしっかりと具体的に結び付けられる「行動の機会」をもっと作らなければいけないと思っています。もちろん、それらの制度に限らず、上長と擦り合わせたものについては、公募のタイミングを待たずとも、うまく経営資源が割り当てられるような設計をしていけるかもポイントになってきます。
我々としては、自分で自律的に考えて、自分で決めて、働ける人が、主体的に「ヤフーにいたい」と思ってもらえるように会社カルチャーや環境を提供したいと考えています。そうすると両者ともに成長できるよね、という考え方は健全ですし、おそらく今後はそうなっていけないと「選ばれる会社」になれないでしょう。
どちらが主従ということは無く、対等な関係を作っていく、それを主導して考えていくのが人事の役割だと考えています。
構成:河原あずさ・西舘聖哉(Potage)