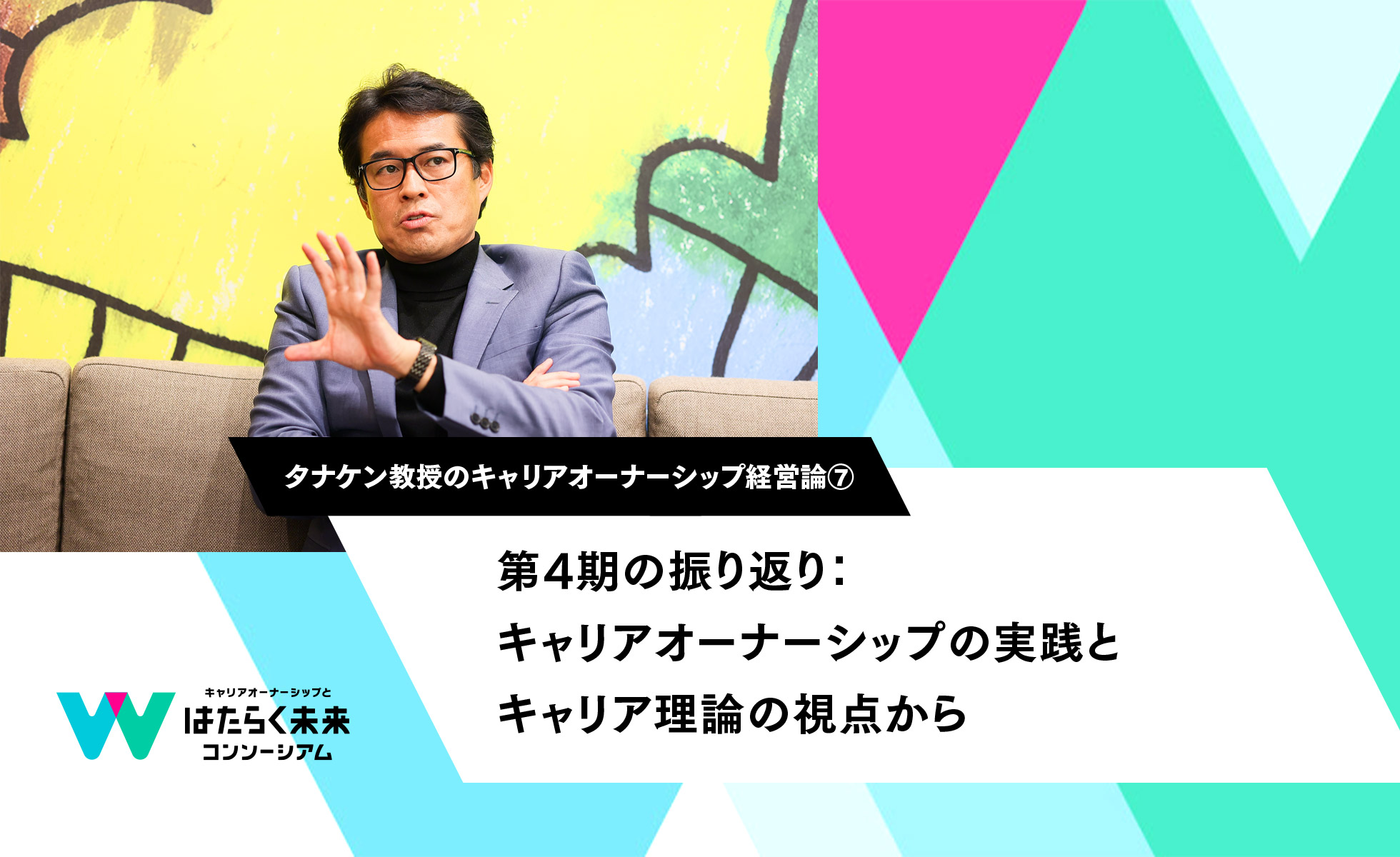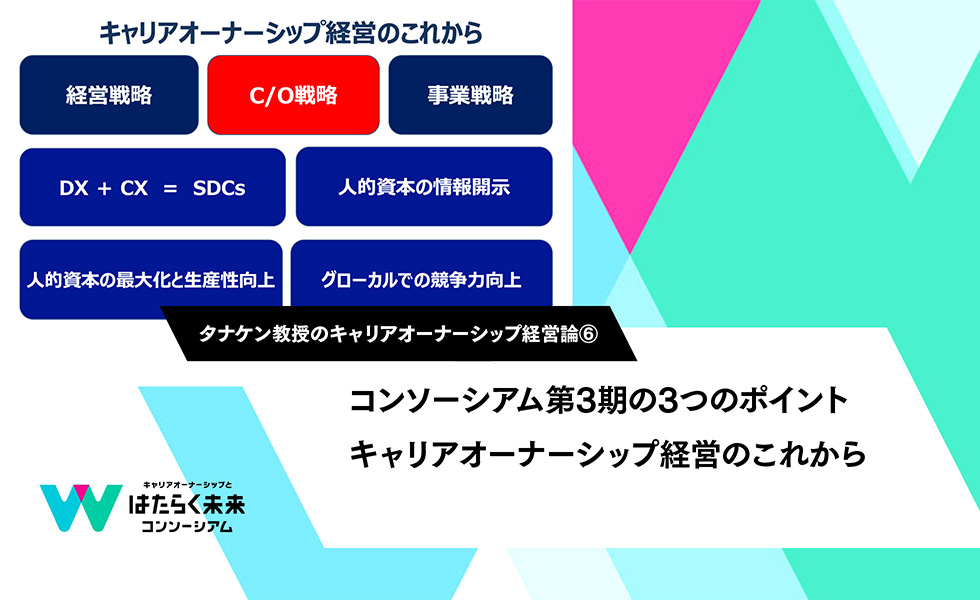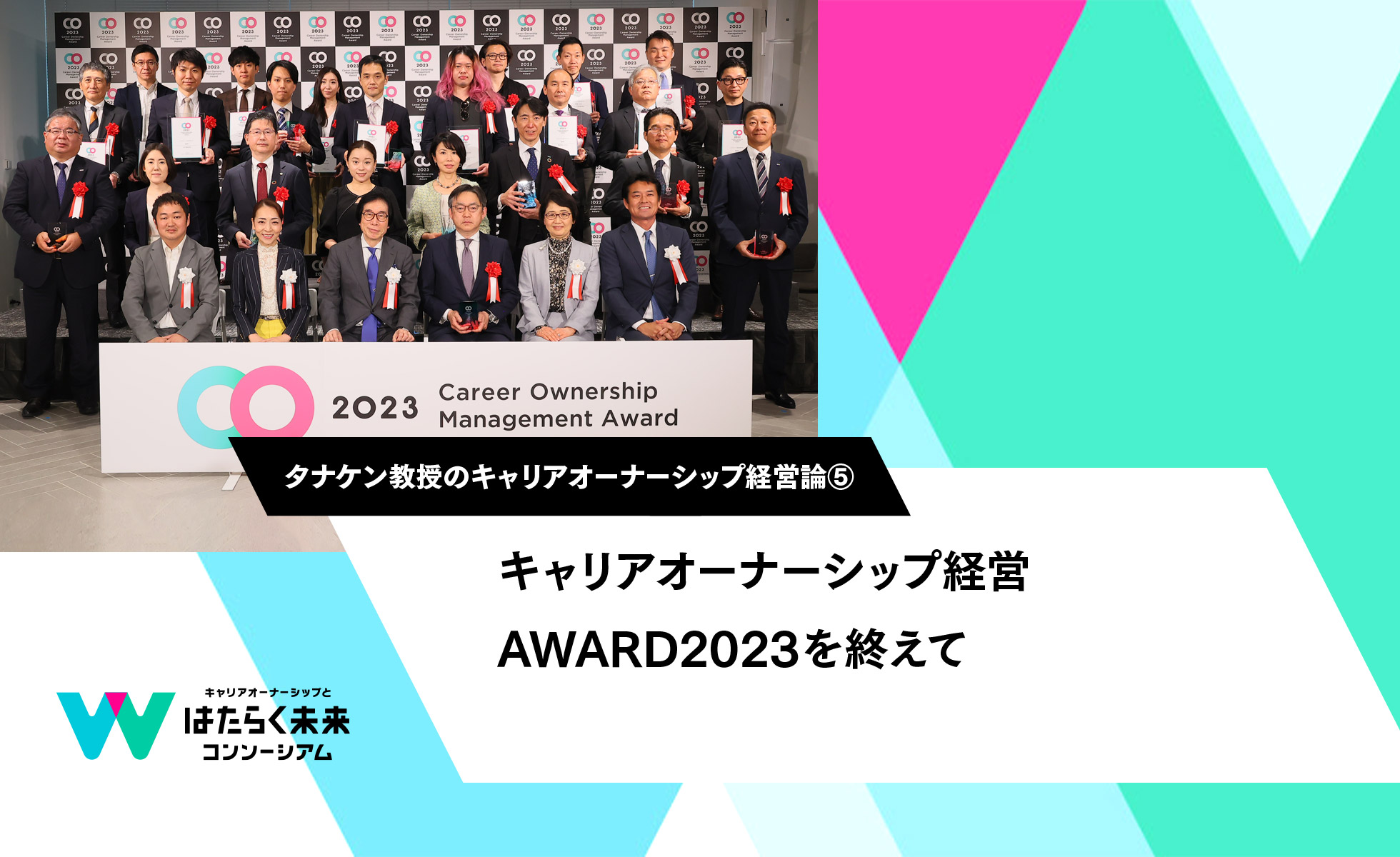「キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム」(以下、本コンソーシアム)は、第4期を迎え、キャリアオーナーシップ経営の社会実装を加速するフェーズへと移行しました。本稿では、第4期の活動を、最先端のキャリア開発およびキャリア理論の観点から振り返り、その成果と課題、今後の展望についてまとめていきます。
第4期は、「キャリアオーナーシップ経営の実践的な適用範囲の拡大と、具体的な成功事例の創出」を主要な目的として設定しました。これまでの議論を踏まえ、実際の組織運営や人材開発における有効な手法の確立を目指したことが特徴です。第1期から第3期までに取り組んできたキャリアオーナーシップ経営に関する問題の設定、現状の分析、課題の解決の蓄積を踏まえて、第4期で、実践の徹底に全体としてコミットしてきました。
そんな第4期をふりかえり、キャリア理論の知見を活用し、各分科会の研究会活動や成果を検証していきます。
※第4期の活動をまとめた「はたらく未来白書2025」はこちら
1)キャリアオーナーシップとキャリア理論の交差点
(1) キャリアオーナーシップの概念と現代キャリア理論
キャリアオーナーシップとは、個人が自らのキャリア形成に主体的に関与し、組織と対等な関係でキャリアを築いていく姿勢を指します。この考え方は、Hall(2004)の「プロティアン・キャリア理論」や、Sullivan & Baruch(2009)の「境界のないキャリア(Boundaryless Career)」に近いです。また、Savickas(2013)の「キャリア構築理論(Career Construction Theory)」の視点からは、キャリアオーナーシップがナラティブ(自己物語)を通じて形成される点にも着目できます。組織にキャリアを預ける従来型のキャリア形成ではなく、自らキャリアのオーナーとなり組織を活かしていく自律型のキャリア形成になります。自律型のキャリア形成のアップデート版として、さらに個人と組織の持続的関係性を戦略的かつ実践的に考え、取り組んでいるのがキャリアオーナーシップ経営になります。
第4期の研究分科会では、これらの理論を背景に、企業がどのようにキャリアオーナーシップを促進できるかについて議論を深めました。
(2) キャリアオーナーシップとエンプロイアビリティ
キャリアオーナーシップの推進には、組織内における個人の「エンプロイアビリティ(Employability)」向上が不可欠です。Fugate et al.(2004)は、エンプロイアビリティを「キャリア資本(知識・スキル・経験)」「適応性」「アイデンティティ」の3要素で構成されるとしました。第4期では、これらを高めるための施策が具体的に検討されました。
2)第4期の活動とその評価
(1) キャリアオーナーシップの組織貢献の見える化
キャリアオーナーシップが企業の事業成果にどのように影響を与えるかを、定量的・定性的に分析する分科会が設置されました。本研究では、企業内でキャリアオーナーシップを発揮する人材の特性を分析し、それが事業貢献にどう結びつくかを明らかにすることを試みました。
分析結果:キャリアオーナーシップが高い人材ほど、組織エンゲージメントが高く、業務遂行力やイノベーション創出力に優れていることが確認されました(Deci & Ryan, 2000の自己決定理論とも整合性があります)。もちろん、課題としては、定量評価の指標の標準化が求められますが、今後もさまざまな指標分析を継続していくことで、より精度の高い定量分析が可能となります。
(2) マネジメント層の意識改革とキャリアオーナーシップの関係
プロティアン・キャリアの文脈では、マネージャーはもはや従業員のキャリアを「管理」するのではなく、キャリアコーチとしての役割を果たすことが求められます(Kidd, 2008)。この視点から、マネジメント層向けの研修プログラムの開発と実施が試みられました。その成果として、マネジメント層が「キャリアオーナーシップの支援者」としての役割を理解し、部下とのキャリア対話の頻度が増加しました。ただ、一部の管理職ではキャリアオーナーシップの概念が浸透しづらく、従来の「安定志向」からの脱却が難しいです。コンソーシアムに参画している企業は、社員数が多く、浸透の深さや時間にも、ラグがあるのが現状です。理想を言えば、「誰一人として、取り残さない」キャリアオーナーシップ経営の実現に向けて、持続的な施策が不可欠となります。
(3) リスキリングとキャリアオーナーシップの統合
本コンソーシアムでは、リスキリング(Reskilling)がキャリアオーナーシップを促進する重要な要素であると位置づけ、学習環境の整備に取り組みました。特に、キャリア・アダプタビリティ(Career Adaptability)(Savickas, 2013)を高めるための施策として、以下の取り組みが実施されました。
3)課題と今後の展望
(1) キャリアオーナーシップの組織文化への定着
従来のヒエラルキー型組織では、キャリアオーナーシップを持つ個人と、組織の期待が必ずしも一致しない場合があります(Hirschi, 2012)。組織文化の変革が必要であり、そのためには組織開発(OD)の視点からのアプローチが求められます。
(2) データドリブンなキャリア開発の確立
第4期では、キャリアオーナーシップと事業貢献の関係性を定量化する取り組みが始まりましたが、さらなるデータ分析が求められます。たとえば、AIを活用したキャリアシミュレーションの導入などが今後のテーマとなります。
(3) 組織と個人の「価値共創」の実現
従業員のキャリアオーナーシップが最大化されたとき、それが企業の利益とどのように結びつくのかを探る必要があります。「人的資本経営(Human Capital Management)」の枠組みの中で、企業と個人がWin-Winとなるモデルを構築することが重要です。
4)これからのキャリアオーナーシップ経営
第4期の活動を通じて、キャリアオーナーシップ経営の有効性が明確になった一方で、組織文化の変革やデータドリブンなアプローチの不足といった課題も明らかになりました。今後は、理論的な枠組みと実務の融合をさらに進め、「キャリアオーナーシップが経営戦略の中核となる社会」の実現を目指す必要があります。これらの知見を活用し、次なるフェーズでは、より実践的なアプローチを強化し、個人と組織の成長が両立する未来のキャリア開発を推進していきます。
第4期の大きな成果に甘んじることなく、私たちは、はたらくすべての人のより良きキャリア形成と、組織の持続的成長、さらにはこの国の再活性化に向けて、集合的な挑戦を続けていきます。
まさに、キャリアオーナーシップで、社会を動かしていくのです。
2025年3月31日
キャリアオーナーシップとはたらく未来コンソーシアム
顧問・田中研之輔
参考文献リスト
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.
- Fugate, M., Kinicki, A. J., & Ashforth, B. E. (2004). Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 14-38.
- Hall, D. T. (2004). The protean career: A quarter-century journey. Journal of Vocational Behavior, 65(1), 1-13.
- Hirschi, A. (2012). The career resources model: An integrative framework for career counsellors. British Journal of Guidance & Counselling, 40(4), 369-383.
- Kidd, J. M. (2008). Career counselling. Oxford University Press.
- Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (2nd ed., pp. 147-183). Wiley.
- Sullivan, S. E., & Baruch, Y. (2009). Advances in career theory and research: A critical review and agenda for future exploration. Journal of Management, 35(6), 1542-1571.